元羽黒
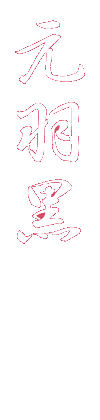

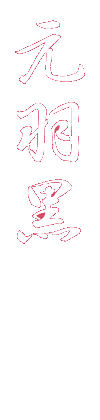

臥牛山南麓の尾根続きの鞍部、ちょうど光徳寺の裏手には、通称「元羽黒」と呼ばれる削平地が残っている。村上の総鎮守、羽黒神社が1633年(寛永10年)まで鎮座していたことに由来する名称であるが、その造作は明らかに中世本庄城の遺構である。もっとも、羽黒神社をこの地に祀ったのは本庄氏なので、旧社地であることに矛盾は生じない。
遺構としては小規模な削平地がいくつかと、それぞれの周囲を取り巻く高さ2~3m程度の切岸が残る。鳥嘴状の土塁が一箇所あるものの、曲輪群を囲郭する意図は希薄で、縄張りの求心性には欠けている。むしろ、軍事的な観点からは、別項で紹介した「八幡山遺構群」と一体となって、尾根伝いに南から進入する敵に備えていたと見るべきだろう。
さて、こうした観点で見たときに注目されるのは、堀切Aの底を通る通称「八幡道」と呼ばれる城道の存在である。光徳寺横から伸びるこの道は、狭いながらも城山の裏表をストレートに結んでいる。城の裏表で兵力を移動させ、機動的な戦闘を行う際には極めて重要な意味を持つ通路だったはずだ。一群の遺構は、この城道の管制も、重要な目的としていたであろう。
さて、あまり知られてはいないのだが、この曲輪群からは、「八幡道」のほかに、臥牛山南斜面を登って山頂近くの帯曲輪群に達する獣道も伸びている(仮称・元羽黒ルート)。現状ではほとんど獣道状態であるが、中世期には非常時の撤退ルート、あるいは出撃路として、きちんと維持されていたに違いない。
しかし、村上城が近世城郭へと改造された際に、道の接続先である山頂部の帯曲輪群は、次第に放棄されていく。これにより、「元羽黒ルート」の存在意義は低下したばかりか、むしろ、「本丸への近道となる軍事上の弱点」として、危険視さえされるようになったはずである。
実際、江戸期に描かれた城絵図には、一切このルートは描かれていない。おそらく近世村上城の建設時に、意図的に放棄されたのであろう。
(初稿:2005.04.01/2稿:2005.05.03/3稿:2005.11.19/最終更新:2017年07月23日)

ガレ場や岩盤のヘリを越える危険なルートが続く。単独行の際は十分に注意
上記のように、本丸へ直登する「仮称・元羽黒ルート」は、近世のごく初期に放棄されたようだ。もともとここにあった羽黒神社を、現在地に遷宮して、みだりに人が入り込まないようにしたのも、旧本庄城時代の城道を、人々の記憶から抹消するのが狙いだったのだろう。
だが、残念ながらその思惑は完全には達成できなかったようだ。というのも、村上城に数ある抜け穴伝説の中には「抜け穴は、山頂から光徳寺へ通じていた」というパターンが存在するのである。詳しくは「抜け穴跡?」の頁を参照して欲しいが、「城道」と「抜け穴」の違いこそあれ、そのルートは「仮称・元羽黒ルート」と全く一緒である。人々の記憶には戦国期「本庄城」の城道の記憶が、形を変えて伝承されたのではあるまいか。
一方、城道を下った先にある光徳寺が、歴代藩主の菩提寺であるというのも興味深い。ひょっとすると、いざ落城となった際には、「秘密の城道を通って城主が光徳寺に入り自決する…」というシナリオが準備されていたのではなかろうか。
