秋葉門復元
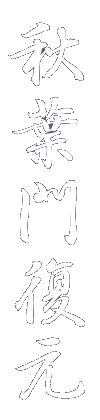
■DATA
建築:1620年頃
破却:1875年
規模:2間半×4間(櫓門時:推定)
2間×5間(藥医門時)
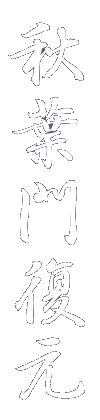
建築:1620年頃
破却:1875年
規模:2間半×4間(櫓門時:推定)
2間×5間(藥医門時)
臥牛山北側に広がる現在の新町一帯は、往時は堀と土塁に囲郭された「準城内」的な武家屋敷街「新町曲輪」であった。4つある廓内への出入り口にはことごとく枡形門が構えられており(※)、秋葉門もその一つである。現在の堀片から新町に向かうS字道路の屈曲部がその跡地に比定される。
ここでは明治元年に描かれた「村上城城門絵図」を参考に、比較的小型の櫓門として復元した。今回は創建当初の古風な意匠を意識して、屋根材を杮葺きとし、壁面も化粧柱を表に見せる真壁造とした。本来は視点位置は武家屋敷の邸内だが、ここでは画面効果を考えて省略した。また、門手前の土橋には堀の水位調整機能もあったようである。明治元年の「村上城城門絵図」には、木樋を通して、オーバーフローを排水していた様子が描かれている。
同じ外郭の門とはいえ、石垣で堅固に固めた二ノ丸、三ノ丸の諸門とはかなり印象が異なる。土塁の緑が美しいのどかな堀端の光景が、城山を借景としつつ続いていたであろう。
さて、上記CGでは櫓門形式で再現した秋葉門であるが、実は何度か形式が変更されている可能性が高い。
詳しい考察は遺構概況の「秋葉門」の頁にまとめたが、築城当初は櫓門形式で築かれた当門であるが、江戸のごく初期になんらかの原因で喪失。一時しのぎに簡易な藥医門形式で再建されたが、1710年代に、もとの櫓門に復された…ということらしい。天守以下、山頂の建造物の再建が断念される中、外郭の門の再建が優先されたあたりに、城の主要機能が防御→示威へと移っていったことがうかがわる。
新町曲輪の諸門が極めて規格性が高いことから、櫓門形式時の当門も、2間半×4間の平面規模だったと推察される。
(初稿:2008.06.28/2稿:2017.07.23/3稿:2017.12.24/最終更新:2018年10月25日)